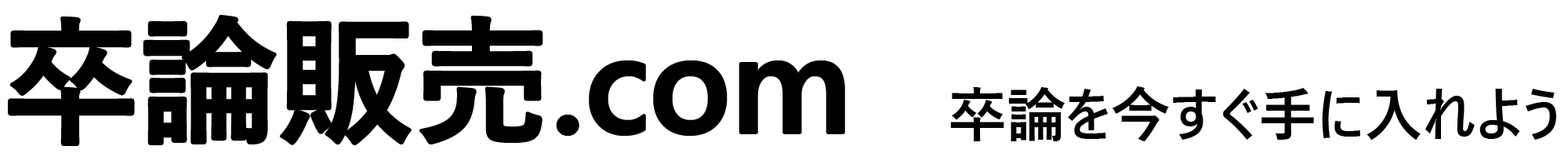卒論で15000字は普通?どれくらいがいいの?
卒論で15000字は普通?どれくらいがいいの?大学生活の集大成ともいえる卒業論文。多くの学生がこの時期に頭を悩ませるテーマの一つが「卒論の文字数」です。卒論には何文字くらいが適切なのか、15000字という数字は果たして普通なのか、学生としては気になるポイントでしょう。今回は、卒論の文字数について掘り下げ、どれくらいの文字数が一般的なのか、また文字数を決める際に考慮すべき要素について考えてみます。
1. 卒論の文字数は大学や学部、テーマによって異なる
まず重要なのは、卒論の文字数が大学や学部によって異なるということです。例えば、文系学部の学生であれば、卒論は一般的に15000字から20000字程度を求められることが多いです。一方、理系や工学系の学部では、実験や研究の成果を報告する形式になることが多いため、文字数が少なくて済むことがあります。この場合、5000字から10000字程度ということも珍しくありません。
大学によっては、卒論の文字数を明確に規定しているところもありますが、必ずしも全ての大学が文字数に関して厳密に指示を出しているわけではありません。そのため、まずは自分が通っている大学や学部の卒論に関するガイドラインを確認することが大切です。
2. 15000字は普通なのか?
15000字というのは、多くの文系学部で一般的に求められる文字数です。特に社会学や経済学、文学などの分野では、このくらいの文字数が適切とされることが多いでしょう。15000字を目標にしていると考えている学生も多いと思いますが、実際にはこの文字数が「普通」なのか「多すぎる」かは、そのテーマの内容にも依存します。
例えば、非常に具体的な事例を分析したり、深い理論的な考察が求められる場合、15000字以上が必要となることもあります。その場合、テーマに十分に対する理解と深掘りができるように、計画的に執筆を進めることが求められます。一方で、より広範なテーマや大枠で議論を進める場合、15000字程度で十分に結論を出すことができることもあります。
3. 文字数を決める際に考慮すべきポイント
卒論の文字数を決める際には、単に「規定の文字数を超えなければならない」といったことにとらわれるのではなく、いくつかの要素を考慮することが大切です。
(1) テーマの範囲
テーマが広ければ広いほど、執筆するために必要な文字数は増える傾向にあります。例えば、国際経済の変動に関する研究を行う場合、単に一国の経済状況だけを分析するよりも多くの資料やデータが必要となり、その分文字数も増えるでしょう。一方で、より特定の事象に焦点を当てる場合は、深く掘り下げることができ、比較的少ない文字数で成果をまとめることが可能です。
(2) 研究の方法
質的研究と量的研究では必要な文字数も異なる場合があります。質的研究では、事例分析やインタビュー、観察結果などを詳細に記述するために多くの文字数が必要になります。逆に、量的研究では統計分析の結果を示すことが中心となり、説明部分が簡潔になるため、比較的文字数は少なくて済むことが多いです。
(3) 指導教員の方針
指導教員が求める卒論の内容にも影響を受けます。指導教員によっては、文字数にこだわることなく内容の充実を重視する場合もあれば、一定の文字数を目標にするよう指導することもあります。そのため、卒論に取り掛かる前に、指導教員と十分に打ち合わせをし、求められる文字数や内容について確認しておくことが重要です。
4. 文字数にとらわれすぎないこと
卒論の執筆において、文字数にこだわりすぎてしまうこともありますが、最も大切なのは内容の充実度です。卒論はあくまで自分の研究成果をまとめたものですから、適切な量で、質の高い内容を伝えることが重要です。
文字数が規定の範囲内であれば、あまり無理に文字数を増やそうとせず、必要な内容をしっかりと伝えることに集中する方が効果的です。逆に、足りない場合は重要なポイントが抜けていないか確認し、足りない部分を補完していくことが求められます。
結論
卒論の文字数に関しては、15000字が普通というわけではなく、大学や学部、テーマによって異なります。自分が取り組んでいるテーマに合った文字数を目指し、内容の充実度を最優先にして進めることが大切です。文字数に過度にこだわることなく、研究を深め、しっかりとした成果をまとめることが、最終的に評価につながります。
▶販売している卒論を見る