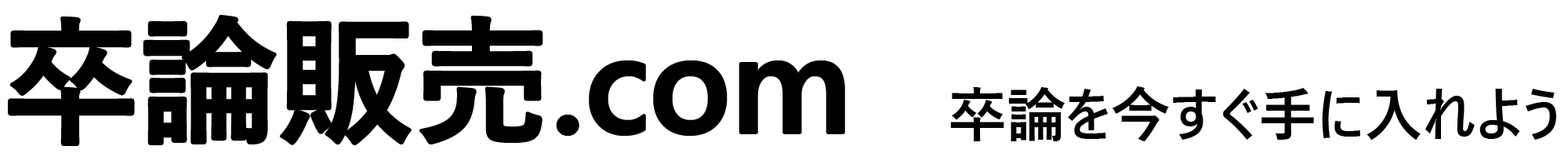卒論、脚注の書き方について、教えます。
卒論における脚注の書き方は、正しい引用や参照を示すために非常に重要です。脚注を使うことで、読者に情報源を明示し、主張を補強することができます。以下に、脚注の基本的な書き方と注意点について説明します。1. 脚注の目的
脚注は、主に以下の目的で使用されます:
引用元の明示:他の研究者や著作から引用した場合、その出典を明確に示す。
補足情報の提供:本文中に詳細を載せるのではなく、補足的な情報や説明を別途提供する。
訳注や解説:外国語の単語や文献についての解説や訳を示す場合。
2. 基本的な脚注の書き方
脚注には、主に2つのスタイルがあり、あなたがどのスタイルを使用するかは、大学や学部の指示に従ってください。代表的なものは「ハーバード方式」や「シカゴスタイル」ですが、一般的な構成を紹介します。
2.1. 引用書籍の脚注の例
書籍を引用する場合の脚注は次のように記載します:
例:
田中太郎『日本の経済』(東京: 日本経済出版社, 2020), 45.
この場合、必要な情報は以下の通りです:
著者名(姓・名順)
書名(イタリックまたは下線で)
出版地
出版社
出版年
引用したページ番号
2.2. 引用雑誌記事の脚注の例
雑誌や論文などの資料を引用する場合は、次のように記載します:
例: 2. 山田花子「企業戦略の変遷」『経済学論集』第30巻、第2号 (2021): 30.
この場合、必要な情報は以下の通りです:
著者名
記事タイトル(引用の場合は、記事タイトルを引用符で囲みます)
雑誌名(イタリックまたは下線で)
巻号・号数
出版年
ページ番号
2.3. ウェブサイトやオンライン資料の脚注の例
ウェブサイトを引用する場合の脚注例は次の通りです:
例: 3. 日本経済新聞社, 「2025年の日本経済予測」日本経済新聞、2025年3月5日、https://www.nikkei.com/article/2025eco(アクセス日:2025年3月6日)。
この場合、必要な情報は以下の通りです:
著者名(または組織名)
記事タイトル
サイト名
発行日
URL
アクセス日
3. 脚注の挿入方法
脚注は、本文中で特定の情報を引用する部分に小さな数字(通常、1, 2, 3...)を挿入し、その数字と一致する脚注をページ下部に記載します。
本文中で脚注を入れたい位置に数字を挿入します。例えば、「...日本の経済は重要な課題です¹。」のように、引用部分の後ろに数字をつけます。
脚注の内容はページ下部に、対応する番号とともに記載します。
4. 注意点
同一の出典を繰り返す場合:同じ資料を再度引用する際、最初の引用時にはフルスタイルで記載し、その後は簡略化した形で脚注を記載します。例えば、2回目以降の引用には「田中、前掲書、60頁」などと記載します。
一貫性を保つ:一度決めた書き方(フォーマット)は、卒論全体を通して一貫して使用します。異なる書式で書くことは避け、指導教員から指定されたスタイルを守りましょう。
必要な情報を漏らさない:特にウェブサイトやオンライン資料を引用する場合、アクセス日を記載するのを忘れないようにしましょう。インターネット上の情報は時間とともに変わるため、どの時点で参照したかを示すことが重要です。
5. 例外的なケース
複数の著者がいる場合:2名以上の著者がいる場合は、最初にすべての著者名を記載し、その後は「et al.」(エト・アル)を使って省略することが一般的です。例:山田太郎、佐藤花子、田中三郎『日本経済論』(東京: 日本経済出版社, 2020)。
6. 結論
脚注は、卒論の質を高め、信頼性を示すために重要な役割を果たします。正確な情報源の記載や適切なスタイルでの脚注を心がけることで、学術的にしっかりとした論文を作成することができます。
▶販売している卒論を見る