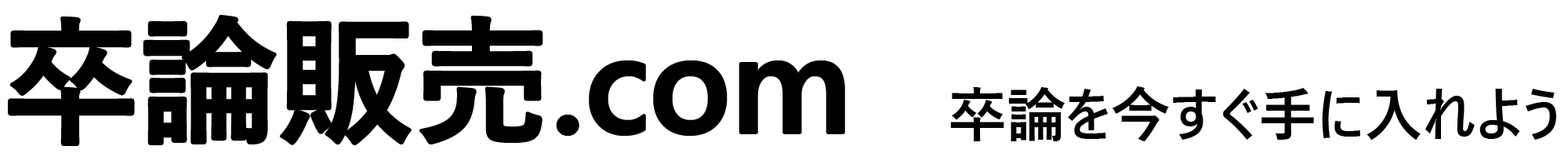卒論で「付録」って何をしたらいいの?
卒論での「付録」は、本文で説明しきれなかった詳細なデータや資料、補足情報などを収めるための部分です。通常、研究の中で必要だけれども、本文中に載せると文章が冗長になったり、流れを壊してしまうような情報を含めます。付録にどんな内容を含めるべきか、具体的に解説します。1. 付録に含めるべき内容
付録には、以下のような内容が含まれることが一般的です:
1.1. 詳細なデータや統計
卒論の研究結果や分析に関連する生データ、統計表、アンケート結果などを示す場合に使います。例えば:
アンケート調査結果:回答者ごとのデータや集計結果
実験結果:実験や調査で得られた数値データ
調査表:フィールドワークやインタビューで得た情報
1.2. 図表やグラフ
卒論内で言及する図表やグラフの元データや補足説明がある場合、これらを付録に含めることができます。特に多くのグラフや図を使っている場合、それらの詳細な説明や元のデータは付録に記載します。
1.3. 調査・インタビューの全文
インタビューや調査の詳細な記録、アンケートの質問項目、調査票などを付録として掲載することができます。これにより、読者が研究方法や結果に対する信頼性を確認できるようにします。
1.4. 使用した調査ツールや質問票
アンケートの質問票や調査を行う際に使用したツール(例えば、調査用のフォームやインタビューのガイドラインなど)を掲載します。これにより、研究手法を明確に示すことができます。
1.5. 追加の計算式や手法の詳細
本文では触れなかったが、研究で用いた計算式や分析方法を詳述する場合もあります。これにより、読者が手法を追いやすくなり、透明性が保たれます。
1.6. 参考文献以外の資料
卒論に関連するが、本文で詳しく言及しなかった関連文献や資料があれば、それを付録に加えることができます。これにより、卒論全体の幅が広がり、より深い研究が示唆されます。
2. 付録の形式
付録を作成する際には、いくつかのポイントに気を付けましょう。
2.1. 番号を付ける
付録の各部分には番号を付けて、本文からも参照しやすくします。例えば、付録A、付録Bのように番号を付け、さらに細かい部分(例えば、アンケート結果の表)には「付録A-1」、「付録A-2」などの番号を付けることが一般的です。
2.2. 説明を加える
付録には簡単な説明や注釈を加えることが推奨されます。何のデータなのか、どのように使うのかがわかりやすくなるように説明を書き添えておきましょう。
2.3. 順番を守る
付録は卒論の最後に配置するのが一般的です。本文が終わった後、参考文献の前に付録をまとめておきます。
2.4. 必要なものだけを収める
付録に入れる内容は、研究を補完するために必要な情報に絞りましょう。冗長にならないように、論文のメインとなる部分に関連する内容を中心に追加します。
3. 付録を使うメリット
付録を上手に使うことで、以下のようなメリットがあります:
詳細なデータを掲載できる:本文が長くなることを避けつつ、必要なデータや証拠をしっかりと示せます。
読みやすさの向上:本文が冗長にならず、読者が研究の流れを理解しやすくなります。
信頼性を向上させる:付録に詳細なデータを載せることで、研究の透明性や信頼性が高まります。
4. 注意点
付録に載せる内容には、以下の点に注意する必要があります:
不必要な情報を載せない:付録はあくまで補足資料なので、必要ない情報を載せると論文が冗長になります。必ず研究内容に関連するものだけに絞りましょう。
説明が不十分な付録はNG:付録に載せた情報は、簡単な説明を加えることが大切です。何のためにその資料が必要なのかを示すことで、読者にとって意味がわかりやすくなります。
まとめ
卒論の付録は、本文で詳細に触れきれない情報を補足するための大切な部分です。調査データ、図表、質問票、分析手法など、研究を支える情報を整理して載せることで、論文全体の質が向上します。付録の使い方を工夫することで、卒論の内容がさらに明確になり、説得力のある研究に仕上がります。
▶販売している卒論を見る